
2023.6.26
【FUN ART LOVERS】Vol.25 マテウシュ・ウルバノヴィチ
紙と鉛筆、水彩だけで クオリティの高い絵を描く。
それが一番の憧れです。
アニメ映画『君の名は。』など数々の作品で背景美術を手掛け、東京下町の古い商店などを描いたイラスト集で知られるポーランド出身のアーティスト、マテウシュ・ウルバノヴィチさん。一枚の絵の中に、そこに住む人々の物語まで描かれているような日本の風景は、世界中の人々を魅了し続けています。アニメや漫画、動画など幅広い分野でも才能を発揮するマテウシュさんに、創作活動への思いとこだわりを伺います。

絵が仕事になることを知ったのは高校生のとき
――子どもの頃はどんなお子さんでしたか。
いろいろなことが好きで、絵を描くことも大好きでした。僕が描いていたのはスーパーヒーローやキャラクターではなく、図面的なものです。絵は自分の周りの世界を分析するための手段というのかな。例えばデスクライトのアームがどうやって曲がっているのかを分析するために描くなど、今思えば、ちょっとアプローチが違っていたかもしれません。
絵は人物よりも、やっぱり物。それは最初からです。アニメや漫画への憧れはずっとあったけど、当時のポーランドはまだソ連の影響下にあり、バットマンもスーパーマンも見たことがありませんでした。テレビに映るものを描いたこともありますが、画面の動きを止めることができないので、難しかったですね。だから、絵は見た物を描く。分析するために描く。スケッチもよくしました。
初めて描いた水彩画は、古城です。なぜか祖父の家にドイツの古いお城の写真が載っている本があって、いいなと思って水彩で描いてみたら、すごくおもしろかった。
うまく描かないと、何を描いているかわからなくなってしまうので、最初の水彩画としては、難しい題材を選んだと思います。森の中や坂の上を表現しないといけないので、それもかなり難しかったですし。しかも、1960年代ぐらいの本だったので、写真のクオリティが低く、細部がよく見えないんです。でも、描いていて、楽しいなと思いました。

――デジタルアートは10代の頃から楽しんでいたのでしょうか?
もともとパソコンや電子機器が好きで、プログラミングにも興味がありました。絵を描くのも好きなので、パソコンで絵を描けるのか?みたいなところで、ソフトを触り始めたのがきっかけです。
僕が10代だった頃のポーランドは、文具や絵の具がすごく高価で、海外の画材もなかなか手に入りませんでした。でも、パソコンがあれば何でも描けるし、クオリティの高いものを描くことができたんですよね。
自分の絵のスキルを使ってお金を稼げることを知ったのは、高校生の頃です。専用のタッチペンなどを使って、紙に描くのと同じようにパソコンで表現できるペンタブレットのイベントが隣の学校であり、それに参加したときのこと。
イベントの最後には、タブレットを自由に触れる時間があったので、僕は一緒に参加した友だちに「こうすると夕焼けになるよ」などと説明しながら絵を描きました。すると、僕の後ろでたくさんの人が僕の絵に見入ってたんです。
その人だかりに気づいたメーカーの方から「タブレットで絵を描くデモをしませんか」と声をかけられました。好きなものを描いて、お金をもらうようになったのはこれがきっかけ。このとき僕は、絵を描くことは趣味にとどまらず、仕事にもなるんだということを知りました。
――その後、神戸芸術工科大学に留学されていますが、大学では何を学ばれていたのですか。
デジタルアートに興味を持つようになった僕は、ポーランドにある日本情報技術大学で、コンピュータグラフィックスを学びました。神戸芸術工科大学に留学したのは漫画とアニメーションを学ぶためで、最初は研究生として在籍。その後、大学院に進みました。
大学では漫画のプロフェッショナルたちが講義をしてくれるのですが、最初は日本語がよくわからなかったので、言葉を理解するのがやっと。かなり大変でした。
まわりには日本の漫画文化に興味のある人たちがたくさんいたので、大学生活では漫画を描いたり、アニメを見たり、作品を深掘りして研究したり。時間はあったので、日本のいろいろなところを見て歩いたりもしました。
卒業制作では短編のアニメーションを作りました。大学の先生から 「あなたの漫画はアニメに似ているから、アニメを作ったら?」と言われたからです。
僕はもともと建物や物を描くのが好きだったのですが、卒業制作で描いた背景画は高く評価されました。新海誠監督が在籍するアニメ製作会社のコミックス・ウェーブ・フィルムに就職できたのも、そのため。僕は背景画家として、入社することになったのです。
――製作会社では、アニメ映画『君の名は。』の背景画に携われたそうですね。
コミックス・ウェーブ・フィルムに入社したのは、ちょうどアニメーション映画の『言の葉の庭』が完成した頃でした。それに参加できなかったのは、すごく残念だったけど、そこから2年ぐらいの間におもしろい作品にいくつか参加しています。
『君の名は。』の制作が始まる頃には、僕も戦力の一人になっていたので、110~120枚くらいは背景画を描いたと思います。『君の名は。』は全体で1200枚くらいの背景が必要だったようなので、僕が描いたのはその10分の1くらい。
それまでは自分一人で絵を描いたり、作品を作っていましたが、チームの一員として絵を描いたのは、社会人になってからです。隣の席には背景監督がいて、少し離れたところには新海監督が座っています。描いた絵が隣の席で直されていくので、いつか修正されずに戻ってくるといいなあというのが、ひとつの目標でした。
僕のスタイルとはちょっと違ったけれど、スタジオのやり方やノウハウなど、いろいろなことを学ばせてもらったと思っています。
人物を描かずにその温かみを描けるのかを試している
――東京のノスタルジックな風景を描いているのはなぜでしょう?
僕はスタジオジブリの作品がすごく好きで、あのスタイルが心に響くんです。東京に来たら、宮崎駿作品をはじめとする日本のアニメの中で見た風景が、全部目の前にあった。初めて来た場所なのに、なんだか懐かしい気持ちになりました。
東京のちょっとゴチャっとしているところも、すごくいいと思いました。人の気配がありそうなのに、家が古かったり。一つひとつに魂が宿っていて、それぞれがまったく違うというのもいいんですよね。
そういう雰囲気にアプローチしたい。人物を描かずに、その温かみを描けるのか。それを試しているのが今の僕です。
――心惹かれる風景に出会うために、何かされていることはありますか。
写真を撮るのも好きなので、散歩に行くときは必ずカメラを持って歩きます。建物や街のおもしろい部分を撮りためて、画像はフォルダに「秋葉原」などと名前をつけて、保存。バックアップもとって、あとで絵の資料になるようにしています。撮ったまま放置していたとか、データを捨てることはありません。自分自身の財産になるものなので、しっかり管理しています。

――紙と手描きにこだわっているのは、どうしてなのでしょう。
アニメーションの背景画はすべてデジタルによる作画でしたけど、自分の作品を描くときはそれとは距離を置く感じで、手描きがいいんだ!みたいなところがありました。
手描きには手描きのよさがある反面、限界もあります。例えば、デジタルの作業では何度でも簡単に描き直せるし、細かい部分を拡大して描き込むこともできます。でも、手描きは、それができない。逆に、この制約があるからこそ、生まれる表現もあり、手描きのメリットといえるかもしれません。
宮崎駿監督の作品にも影響を受けています。僕はシンプルなものに憧れがあって、紙と鉛筆、水彩だけで世界を描けるのは、すごく素敵なことだと思っています。そこに憧れを抱いて、鉛筆や水彩で自分の絵を描けるかどうか、とりあえずやってみようと思って。
でも、デジタルと手描きをミックスすることもありますよ。例えば、東京の下町にある古い建物を描いた『東京店構え』(エムディエヌコーポレーション)もそう。デジタルなら何度でもやり直しがきくので、下書きとして色を試したり、イメージを視覚化したり。そういった使い方をしています。

水彩セットと折りたたみの椅子をバックパックに詰め、野外スケッチに行くことも。
――画材へのこだわりはありますか。
最近はエコについて考えるようになりました。道具もできるだけ買い替えないようにしています。もう60年くらい前のものですが、祖父が使っていたボールペンを今は僕が使っていて、こんなふうに1本買ったら、芯を替えるだけで何十年も使えるようなものが理想。環境に影響を与えそうなもの、使い捨てのものはなるべく控えたいなと思っています。
自分にちょっとエコ的なリミッターはかけていますが、画材をあれこれ試すのが好きなので、いつも何かしらの実験をしています。最近だと鉛筆のかわりにボールペンを使ってみたり、水彩の上にマーカーを重ねたり。新しいことを探求するのは楽しいし、好きですね。
あとはやっぱりクオリティです。僕が使う画材は、基本的に紙と鉛筆、ペン、水彩。シンプルだけど、これがあればクオリティの高いものを何でも作れるみたいなのは、一番の憧れです。
水彩画はすごく簡単で、いろいろな表現ができるのだけど、やはりスキルが必要です。プランニングも必要で、最初からその絵のイメージがないといけない。『東京夜行』(エムディエヌコーポレーション)を描いたのは、水彩で表現するのが一番難しい夜景の光を描けるか、その勝負魂からでした。

水彩にマーカーのニュアンスをプラスした初めての絵。使い方を模索するのも楽しい時間。
アート作りは仕事だ。その言葉を心に刻みながら。
――日々の創作活動の中で、喜びを感じるのはどんなときでしょうか?
今までの僕だと、回答は、目に見えるものをうまく表現できたとき。アニメの背景を描くのもそうですし、撮影したものを紙の上に絵として表現するのもそうです。自分の目で見たお店を、僕というフィルターを通してうまく表現できたときに、喜びを感じます。
ただ、最近は少し変わってきました。今の僕は、目で見えるものではなく、自分が創造して描いたものを作品の中心にしたいと思っていて、そのクリエイティビティがうまくいったときは、すごくうれしい。目で見たお店ではなく、実在しないお店を描いても、その存在感をうまく表現できたり、嘘っぽくならないように描けたりすると、いい仕事ができたと思えるんです。でも、それは簡単ではありません。
職人的に絵を描くスキルは、年月をかければ誰でも持てると思います。見えるものを紙に写す技術は、頑張れば磨けますが、何を描くのか、どう描くのかを考えるのは、まったく違う分野だということに気づきました。イマジネーションを駆使して、作品の幅を広げていこうと頑張っているところですが、やっぱり難しい。難しいけど、うまくいったときは楽しいですね。
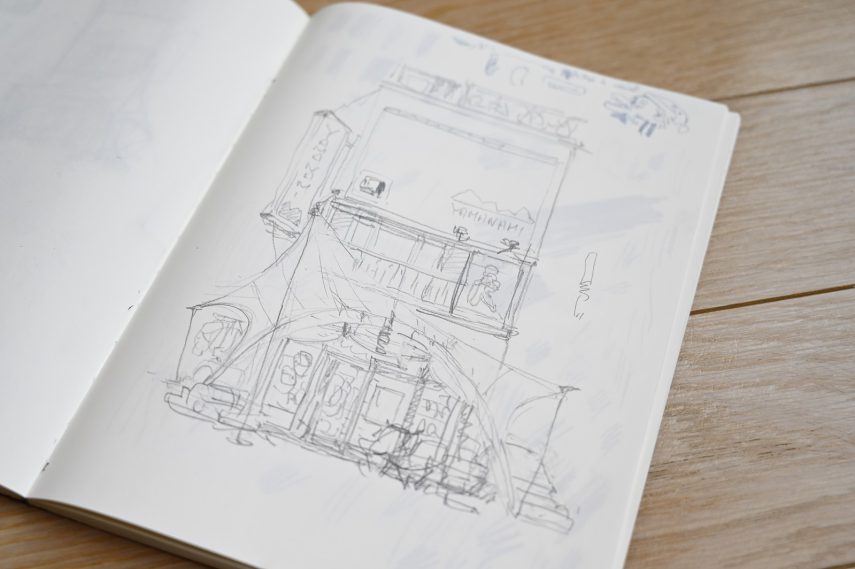

3年がかりで制作した最新の作品集は、実在しないお店がテーマ。写真の絵はそのなかの1点。
――創作活動を支えるエネルギーの源とは?
それも変わってきました。以前は写真や、自分の身の回りにある世界から知識を得ていたのですが、最近はそれを意識しながら、考える時間を作ることを大切にしています。
かつての僕は、何かを描く。とりあえず描いてみる。写真を選んで描き、はい、次、といったように、描こうという気持ちが原動力になっていたのだと思います。枚数もたくさん描きましたしね。
でも、今は自分が何を描きたいのか、何を表現したいのか。気持ちや空気感を描くことができるのか。そうやって悩みながら描くことが、原動力になっている気がします。
――これからチャレンジしたいことはありますか。
長編のマンガを描きたいと思っています。先日、国内外で活動している11人のクリエイターで、日本を舞台にした『日月十譚』(トゥーヴァージンズ)という漫画の短編集を制作しました。ひとり16~18ページくらいの作品を描いて、なんとなくその世界観を作り上げることができた。もっと長いものができそうな手応えがあったので、長編漫画への取り組みは僕にとって新たな勝負になると思います。
――『FUN ART』という言葉から連想することを教えてください。
「若さ」かな。若いうちは純粋にアートを楽しむというか、ダンスを自由に楽しんだり、スポーツを自由に楽しんだりするのと同じように、アートを自由に楽しむことができます。楽しければ、それでOK! そんな感じで。
もちろん、大人になっても、プロになっても、ある程度は楽しむことは大切ですが、プロのアーティストになると、そればかりではありません。自分の作品が世に出たときに、他の人に与える影響も考えないといけないので、ときにはFUNではないアートを作らなければならないこともあります。
自分が描いていても楽しいと感じないこともあるし、見る人もおもしろいと感じないこともある。その逆もある。人に与える影響を考えるのは、とても大事なことだと思っています。

――楽しく創作活動を続けるコツはありますか。
細かいことに気づくことが大切だと思います。1本の線をうまく描けたことでもいいし、ここは描くのが楽しかった、ここはうまく色を塗れた、そういったことは楽しい気持ちに火をつける燃料になると思うんですね。
僕の中にも、アート作りは楽しくないといけないというイメージがありました。でも、それが逆に自分の苦しみにもなるんです。僕は今、全然楽しくないのに、なぜこれを描いているのだろうと思ったり。
僕が思っている難しい話を絵を使って伝えようとすると、当然それは難しいので、悩みつつ、苦しみながらもがいていることが多い。それは「楽しい」気持ちとは真逆です。だからこそ、「この線はうまく描けた」と自分で意識的に気づかないといけないんですよね。
宮崎駿監督が、「アニメーターは、例えばこの草をうまくゆらゆらさせただけで、1週間はモチベーションを保てる」というようなお話しをしていましたが、まさにそのとおり。
僕の仕事机の横には「Making Art is Work(アート作りは仕事だ)」と書いた紙が貼ってあります。仕事としての難しさやつらさはしっかり受け入れ、うまくできたことは自分で意識して気づくようにする。これはとても大事じゃないかな。

――最後に、Fun Art Studioの読者のみなさんへメッセージをお願いします。
絵を描いて、その絵をInstagramやpixivにアップしたら、それを見た100人、200人の人に何かしらの影響を与えます。自分が楽しむことは大切ですし、作品を見た人が「楽しいね」「これいいね」と思ってくれたら、それでいい。でも、自分が楽しんで作っていても、他の人によくない影響を与えることもあるので、それを意識しておくと、作品作りのヒントになると思います。
それから、もうひとつ。絵を描くのが好きな人でも、思うように描けないようなことがあると思います。でも、それは当たり前のこと。誰だったかは忘れてしまいましたが、ある小説家が言っていました。「うまく表現できないときは、自分のペンの中に、1万個のよくない言葉入っていると思えばいい。まず、それを出す。書いて、書いて、書きまくって、よくないものを出したら、あとにはいいものが入っているはずだ」と。
絵を描くのも同じです。自分の描いたものがいまひとつだと感じたら、それは自分のスキルよりも、アートセンスのほうが高いということ。善し悪しがわかっていれば、伸びしろもあるし、進むべき方向もわかっている。うまくいかなかったからといって凹むのではなく、それは自分の手のスキルがまだ、アートセンスに追いついていないということです。描いて、描いて、ダメなものを出し続ければ、だんだんといいもの割合が増えていきます。思い描いたイメージがあるなら、とにかく練習あるのみ。完璧とまではいかなくても、きっと思い描いたイメージに近づくことができると思います。
最近は世の中の流れがとても速くなっています。そんな時代だからこそ、ゆっくり時間をかけて一枚の絵を描く。そういった活動が大切になっている気がします。


Profile
マテウシュ・ウルバノヴィチ
日本を拠点に活動する、ポーランド出身のイラストレーター。アニメーションや漫画を学ぶため、神戸芸術工科大学に留学。大学院を修了した2013年には、アニメ製作会社のコミックス・ウェーブ・フィルムに入社。背景美術の美しさで定評のある新海誠監督のもと、アニメ映画『君の名は。』など、数々の作品の背景画の作画に携わる。独⽴後、『東京店構え』『東京夜⾏』などの手描きの作品集を刊行し、ロングセラーに。絵画、イラスト、アニメーション、コミック、動画など、幅広いジャンルを手がけ、インターネットでも作品を公開。世界中に多くのファンを持つ。
https://mateuszurbanowicz.com/
取材・文/小山まゆみ
撮影/樋渡 創




